
まず最初にバイクの免許取得、本当におめでとうございます。『バイクに乗りたい』という気持ちを叶えるためには本当に多くのハードルを超えてきたと思います。
とにかく物入りで、免許取得やバイク購入だけでも多くの資金が必要だったのではないでしょうか。
さらに、バイクライフを楽しむためにもいろいろアイテムが必要になってくるのですが、いちライダーとして20年過ごしてきた中で実はいらなかった、不要なものにもたくさん投じてきて反省を繰り返しています。
ここではそんな数多くの失敗から、今だからこそ伝えられるビギナーに本当に必要なものだけをセレクトしてお伝えしたいと思います。
そこで今回のテーマは『ヘルメット選び』。このメッセージを受け取ったあなたには安全で素敵なバイクライフを送ってほしいと願っています。
バイクの次に必要なアイテムはヘルメットです。法律的にもヘルメットの着用が義務付けられています。
最初に必要なアイテムなのに、いきなり安くはないアイテム。どう選べばいいのでしょうか?

まず「バイクのジャンルにあったヘルメットを」と巷では言われているそうですが、ビギナーこそフルフェイスをお勧めしています。
乗っているバイクがどんなジャンルであれ、フルフェイスは一つ持って置いて絶対に損はありません。
免許を取得したばかりでバイク走行経験が浅い間は、どこでどのような危険が潜んでいるか分かりづらいものです。
転倒時に保護力があることはきっと誰にでも理解できると思うので、ここでは想定外のトラブルエピソードをシェアさせてください。
まず『目』です。ノーヘルがOKなアメリカにでさえも、ゴーグルだけは法律で着用が義務付けられている州があるほど。実にアメリカらしいのですが、
「事故って自分が死ぬのはどうぞご勝手に。でもゴーグルせずに万が一虫や石が目に入り、視覚を失い人を巻き込むのはとても罪深いことだよね」と。かなり厳しく罰則されます。
日本の道でも、山を走ればたくさんの虫が飛び込んできますし、砂利やチリが目に入ると大変です。すぐに止まれるような道だといいのですが、なかなか都合よくいないものです。走行中に目を開けられない恐怖体験はしたくないものです。
異物が飛び込んでくるのは、目だけではなく場合によっては鼻の穴にも飛び込んでくることさえあります。経験が浅い時期だと、初めてのトラブルにたいしてもどう対処したらいいかわらず結構大変な思いをします(しました笑)。
警察官からある珍事件について聞いた話があるのですが、なんとカナブンが鼻から突き抜けて脳にまで到達してしまった事件もあったそうです。あらゆることが想定されるバイクライフ。フルフェイスは広い守備範囲でライダーを守ってくれます。
虫(木にぶら下がる毛虫も注意)、砂利、チリ、2ストロークバイクのオイル混じりの排煙、鳥、鳥フン、外壁塗装中のペンキ、自宅前の水打ちをする人の撒く水、花木への水やり中のホースからの水、水たまりを避けずに走る車が押し出す大量の水、スーパーや菓子パンのゴミ袋、などなど。私がすべて経験したことのある飛来物です。
単に、コケた時を想定してもフルフェイスの防御力が圧倒的なのですがさまざまな珍事件にも幅広く対応してくれるのがフルフェイスだと思っています。

ジェットヘルメットのいいところは視界が広く、景色を楽しみやすいことで個人的にも好きなモデルの一つでもあります。
スクリーンを装着しない場合は、ゴーグルやフェイスマスク、ネックウォーマーなどで顔面の露出を少なくできるアイテムを着用すれば解決します。
< STAY RIDERの一押し!アイテム >
ちなみに白バイ隊員はジェットヘルメットです。視野が広くなることで守備範囲が広くなるからではないでしょうか。
その他ジェットヘルメットのいいところは、特に暑い夏の信号待ちなどスクリーンを開けるだけで涼しく開放的になれます。ヘルメットを被ったまま水分補給もできるし、軽い軽食もできるのがすばらしい点です。
デメリットがあるとすれば、顎が露出しているのでその範囲に強い衝撃があった時には怪我につながる可能性があります。

開放感は最高です。あの開放感は他のどのヘルメットにもかないません。ただ顔面や顎だけでなく、耳まで露出しているのでビギナーにはやはりお勧めはしません。
アメリカンなバイクなど、半ヘルがよく似合うし、ネイキッドでもちょっと族車っぽい仕様が好きな場合には半ヘルを被りたい気持ち、よくわかります。ただ、真冬の走行を考えたときには似合うとか似合わないとか言っていられないほど寒いです。
リード工業から出ているハーフ D’LOOSE という半ヘルを見ても分かる通り、半ヘルは規格がPSC・SG(125㏄以下用)ということもあり中型バイク以上のバイクには不適格となります。
正直、どのヘルメットも同じに見えませんか?それが全然違います。いろいろ試してわかったのは、やはり最終的には信頼のメーカーを選ぶことです。
私が最初に手にしたのはAraiでした。4万円ほどしたのを覚えています。確かに安くはないのですが、これはもう保険だと思って思い切って書いました。我ながらいい判断をしたと今でも感じています。
日本を代表するメーカー、といより世界トップメーカーのヘルメットなのでどれ買っても当たりです。唯一、判断を失敗したと思ったのはカラーです。かっこいいのでブラックを選んだのですが、夏はかなり暑かったです。それはのちに白いヘルメットにしてから気がつきました。
レーサーの方との交流の中で、皆が口をそろえていっているのはAraiヘルメットの被り心地は最高だということです。そんな話を聞くとまたAraiに気持ちが傾いてきます。
「じゃSHOEIはどうなの?」正直、SHOEIの被り心地も最高でした。ちなみに今わたしが愛用しているのはGlamsterのホワイトです。
このヘルメットを選んだ理由は、なんと言っても軽い!ことです。その上フォルムが美しく、被った時の体とのバランスが非常にいいんです。ぜひ一度フィッティングしてみてほしいヘルメットの一つです。
HJC製のヘルメットも長らく使用していた経験があります。このメーカーは日本のお隣、韓国のメーカーです。当時、HJCを選んだ理由としてはリーズナブルな価格も魅力でした。国産2大メーカー、Arai、SHOEIよりもやや安くてデザインも豊富。かつMOTO GPなどのレースシーンでも多くのレーサーが使用していることからも信頼のおけるメーカーの一つです。
ハイエンドモデルのRPHAシリーズもチェックしておきたいところです。品数が多くみていて楽しいのもHJCの特徴とも言えるでしょう。
ヤマハ発動機のバイクアクセサリーメーカーの子会社『Y’S GEAR』のラインナップの一つにZENITHというヘルメットブランドがあります。製造はいまはHJCが担っているそうです。その意味では、ヤマハが選ぶわけですからHJCの品質も十分あるということが伺えます。
一方で、暗黙の了解としては『ヤマハ』ブランドなのでヤマハ以外のバイクに乗っている場合にそうしたチグハグが気になることもあるかもしれません。事前に知っておくといいでしょう。
後で知ると「え、ホンダ党なのにヤマハブランドのヘルメット買っちゃった!?」とショックを受けることもあるかもしれません。メーカーの垣根にこだわらなければ優良ヘルメットです。
OGKという大阪に本社をおくヘルメットメーカー。1982年からバイクや自転車のヘルメットの製造を始め、2006年にオージーケーカブトに会社名を変更しました。
KABUTOもレースでの実績が豊富にあります。私がバイクに乗り始めた時はまだOGKというロゴが入っていてシンプルなデザインでした。
今は、カラーリングも含めてスポーツバイクやネイキッドに似合うようなデザインが多く出されています。
1947年に誕生したイタリアのヘルメットメーカーです。AGVヘルメットの魅力は、日本にない感性から生まれるデザイン力です。
ただ注意してほしいのはサイズです。欧州メーカーはアジアンフィットというアジア人向けの形状になったモデルがあります。
日本では、ダイネーゼというバイクギアメーカーショップが一緒にAGVヘルメットの販売もしています。ダイネーゼショップや量販店で取扱があれば試着できるのでぜひフィット感を確かめてください。
個人的な印象としては、日本の老舗メーカーの作りとはやはりニュアンスが違いました。被ってみた印象に従って、自分の頭にフィットするものを選ぶとよいでしょう。
1957年に誕生したアメリカのヘルメットメーカーです。現代のフルフェイスの元となったとされるSTARというモデルもBELLの作品です。
ネオクラシックブームにより、この手のヴィンテージ感のあるデザインが似合うバイクが現代にも多くラインナップされるようになりました。
アメリカのメーカーということもあり、やはりハーレー乗りなどに人気ですが、最近のフルフェイスのデザインがなかなかかっこよくて実は私も狙っています。
Japan Form(ジャパンフォーム)と言われる、日本人の平均的な頭蓋骨の形状に合わせた作りになっているのも嬉しいところです。日本各地にBELLの販売代理店があるのでまずは試着からしてみるといいでしょう。
<BELLヘルメットのおすすめモデル!>

アメリカのレースシーン、特にドラッグレースにおいてシンプソンなくして語ることは難しいでしょう。レーシングアイテムの供給は1950年台からスタートし、その後1979年にヘルメットの製造をしています。
そこで誕生したのがなんともワイルド(悪そう)で強そうな印象を与えるアイコニックなヘルメット、M30。今でもバンディットというモデルとしてもシンプソンの代名詞になっています。悪くなってみたい青少年たちの憧れのヘルメット、とも言えます。
フランスのマルセイユに本社を置くヘルメットメーカーです。レースでの実績もありフルフェイスはスポーツバイク寄りのデザインが豊富にあります。
フルフェイスもさることながら、ジェッドヘルメットに近いモデルでゴーグルとマスクが付属されているDRAK(ダラク)というモデルがなかなかアイコニックで都会的なスタイルが好みの人にはきっとハマると思います。ハスクバーナ、KTMなどの欧州車には特によく似合います。

実は、今現在このKYTのSTRIKE EAGLEというヘルメットも愛用しています。他の人からは「え、何そのメーカー?」「被ってる人初めてみた」とかよく言われます。
イタリアデザイン、インドネシア生産のヘルメットです。というと、「それ安全なのか?」といわれますがSG規格にちゃんと合格しています。
いま私が所有しているバイクが、オフロード、ネイキッド、カフェレーサーとジャンルがバラバラです。
できればそれぞれに合うヘルメットが欲しいと思って探してしたのですが、結局このKYTのオフロードヘルメットのバイザー部分を取り外してゴーグルをつけてセミフルフェイスのようなスタイルに着地しました。
オフロードのヘルメットはとにかく軽くて涼しいので好きです。ただ、その分風や音が容赦なく入り込むので高速走行には不向きです。
その場合にはやっぱりフルフェイスが安心感もあるし、何より楽で疲れにくいです。
<KYTヘルメットのおすすめモデル!>
SG規格は、安全性の規格で今回ここに挙げているヘルメットはすべてSG規格認定のヘルメットです。
ただし、中止なければならないのはインターネットでの購入する場合です。並行輸入品などはこのSGマークがないこともあります。量販店や海外製品であれば日本の代理店が卸しているショップなどで購入するのが一番安心です。
ヘルメットの安全性を確かめるための一つの基準としてこのマークがあるか、ないかを事前に確かめておくとよいでしょう。

(画像元:一般財団法人製品安全協会)
各メーカーが、いろいろなコンセプトでさまざまなラインナップを用意しているのを見ているうちに段々と欲しいと思えるヘルメットがわかってきたでしょうか。
購入できる場所としては、量販店、バイクショップ、ディーラーの他、インターネットでも購入できます。
実店舗などオフラインで購入、あるいはインターネットのオンラインでの購入。どちらでも欲しいものが手に入ればよいと思います。
私の失敗談としては、海外サイトでアジアンフィットであるか否かを確認せずに買ってしまったことが挙げられます。アジアンフィットではないヘルメットは、長時間かぶっていると頭が痛くなりツーリング中はなかなかの苦行になった思い出もあります。
お店で買う場合、インターネットで買う場合それぞれでどんなメリットとデメリットがあるのか見てみましょう。
これがベストだと思います。実際に試着できてフィット感もわかるし、バイクに乗る時のファッションに合うかどうかもイメージしやすいです。
スタッフの方に聞けばいろいろと教えてくれるはずです。ほしいと思える在庫があればそのまま買って帰れば帰り道もきっと楽しくなります。
神奈川県の企業で、自動車部品の卸、小売や用品販売を1962年から行なっています。
1978年にクルマ、バイクの用品販売からスタートした埼玉に本社を構える会社です。今現在はイエローハットの傘下にあるた、四輪用品専門店イエローハットと併設されるケースもよくあります。
1992年創業のバイク用品会社です。世界最大級のバイク用品店として千葉県の柏市に1号店を構えます。
東京都の東雲にあるTOKYO BAY 東雲店はライダーがどこからともなく集まってくるスポットとしても有名になりました。
1951年創業の大阪に本社を置くバイク用品の会社です。戦後のバイク需要に合わせて成長を遂げた会社で、『オートバイ部品のデパート』と看板を掲げて小売をしていたそうです。日本初の二輪専門洋品店のフランチャイズチェーン店化したことを考えると魁的な老舗と言えます。
全国チェーン、というわけではないのですがオフローダーたちにとっては無視できない用品品店です。
神奈川県の横浜市、川崎市にお店を構えています。スタートは1982年、二輪タイヤ専門ショップとして始まりました。そして、オフロード用品を扱う用品店を出し、その後用品メーカーになりツーリング用品をリリースし有名になりました。
オフロードにルーツがあることからも、今もオフロード関連の用品が多くありオフ車乗りには楽しい場所でもあります。
用品店にいって、欲しかったヘルメットののデザインとサイズがないなどの場合にはインターネットで買っていました。やはりECは便利だし早い。ただその分、ドラマが少ないので個人的には用品店で見つけて買いたいという気持ちがあります。
悩ましい質問ですが、お答えします。お店の方たちからするとあまり気持ちのいいことではないと思います。
あれだけ在庫を抱えて並べて、お客さんにも触れてもらうということは、責任あるスタッフ以外の人が触るわけですからそれだけリスクもあります。
ましては扱い方を知らない人が、被って遊んで知らないうちに落として黙って戻していた、なんてことを考えると結構神経を使うところでもあります。
その意味では、試着もさせてくれて、たくさん品揃えもしてくれてありがとう、という気持ちも込めてできるだけお店で買うようにはしています。
あまりにもマナーが悪い人が増えたら、お店も試着を有料にしてしまうなど対応策を考えなくてはなりませんし、そうなったら残念です。
いい環境を維持するためにも、いい客でもありたいというのが私の思いです。
でも、お店の在庫にない、あるいは店員の対応があまりにも悪すぎた、という場合にはインターネットの方が気持ちよく購入できることもあるので、お互い気持ちよくいられる手段で購入するのがベストだと考えています。
自分の頭を守ることを目的にヘルメットを被る、という観点から中古品はお勧めしません。絶対に。
ヘルメットって、一度でも落としてしまったら使い物になりません。ヘルメットは衝撃を吸収して頭へのダメージを最小限にしてくれています。
もしたった一度でも衝撃が加わったヘルメットは、衝撃をダイレクトに頭に伝えてしまいます。
試しに、使い古されたアライのヘルメットの落下テストをしたことがあります。
そうするとどうなるのでしょうか??
答え:落下したヘルメットが地面に到達するなり、上に跳ね返ってくる。
新品のヘルメットであれば衝撃を吸収して跳ね返ってくることはありません。
どれだけ世界一のメーカーが作ったヘルメットととは言え、役目を終えたヘルメットはあなたの大事な頭を守ることは不可能です。
中古品のリスクはそこにあります。トップメーカーのヘルメットとは言え、知らないうちに衝撃が加わっていればいざという時に本来の品質で保護はしてくれませんから。ちなみにレースの世界では、一度でも落下などの衝撃が加わったヘルメットの使用はご法度です。
初心者ライダーであれば、なおさら新品のヘルメットを購入してほしいと思います。
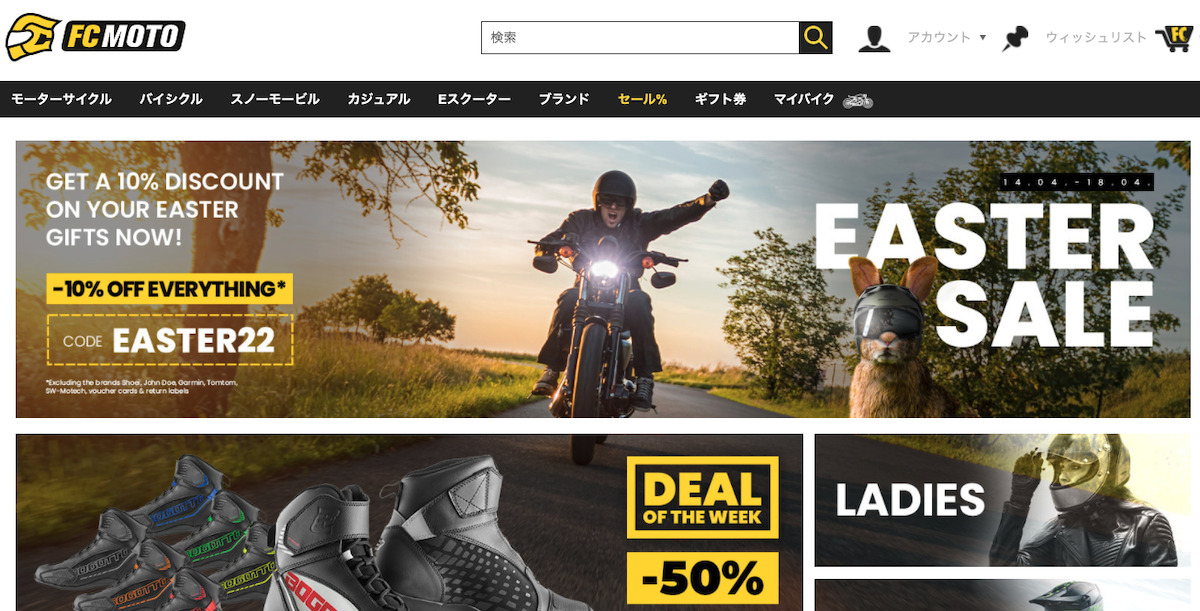
これも経験があるのでお答えしますね。FC-MOTOでの購入体験で唯一失敗したのがヘルメットです。
HJCのヘルメットを買いました。かっこいいモデルが、日本で買うよりもはるかに安かったんです。ラッキーと思っていました。
商品が届いて被ってみたらサイズも問題ない、と思っていました。でもいざツーリングに行くと、ちょうどぴったり1時間後に頭痛がします。おかしいな。
実は、ヨーロッパ人の頭蓋骨の形に合わせてあるので日本人の頭にはフィットしていませんでした。
日本人が海外製のヘルメットを買うときには必ず『アジアンフィット』を選ぶようにしましょう。
1時間を超えた走行になると苦痛です。楽しむためにバイクに乗っているのか、修行のために乗っているのかわからなくなります。
そうならなたいためにも、やはりヘルメットは試着して自分のサイズにあったヘルメットを、もっと言えば相性のいいメーカーやモデルが見つかれば最高です。
ここまでで、たくさんあるメーカーそれぞれの特徴や買える場所もなんとなくわかってきたのではないでしょうか?
最後にバイクヘルメットのコーディネートについて少し触れてみたいと思います。
大きく二通りの選び方があります。
このどちらかに従っておけば外してしまうことはほぼありません。
これから乗ろうとしているバイクのカラーは何色でしょうか?ブラック、ホワイト、レッド、グリーン、ブルー。いろいろあると思います。
バイクのイメージカラーに合わせておけば大体まとまります。
レッド、ブルー、グリーンなどの車体カラーにヘルメットの色を合わせる場合には、『差し色』としてバイクに施されるイメージカラー含まれているくらいがちょうどいいバランスに収まりやすいです。
例えば、ブラックベースのヘルメットにレッドの差し色が入ったものや、白ベースのヘルメットに青の差し色が入ったものなど。
ベースが白や黒だとどのバイクにも合わせやすいです。
黒と白、それぞれ着用してもっとも差がでるのは夏です。黒は何と言っても暑い。それでもかっこいいから我慢してでもブラックがいい、という気持ちもよくわかります。
ここ数年は長らくホワイトを選び続けているのですが、そろそろ黒が欲しくなります。黒いヘルメットのいいところは引き締まって見えるのでスマートな印象になることです。
ジャケットの色に合わせておくと、どのバイクにまたがってもサマになります。ただ、茶色や赤色のジャケットの場合は、バイクのカラーに合わせた方がまとまると思います。
個人的には赤や青のジャケットにはホワイトが爽やかに引き締まるので好みのコンビネーションです。
「カラーで合わせることはわかった、でもアメリカンとスポーツバイクでは合うヘルメットも違うでしょ?」
私も同感です。この場合の合わせ方として、バイクとヘルメットのカテゴリーの一致をさせると良いです。
カテゴリーを大きく三つのカテゴリーに分けてみたいと思います。
クラシックのジャンルに入るのは、アメリカンやカフェレーサーなど英国クラシックなバイクです。
具体的には、ハーレーやトライアンフはもちろん、ホンダ スティード、ヤマハ ドラッグスター、ホンダ GB系、ヤマハSRなど。
これらのバイクには、クラシックなBELLのSTARやネオクラシックモデルとして最近出ているSHOEIのGlamster(グラムスター)、AraiのRAPIDE(ラパイド)などがあります。
モダンスポーツのジャンルに入るバイクは、Kawasaki ZX系、Yamaha R系、MT系、あるいはHonda CBR系、SUZUKIのGSX系などのネイキッドやスポーツバイクです。
SHOEIであれば、X Fourteenや、RX-7Xなどの定番フルフェイスがキマります。
Kawasaki KLX、Yamaha Serow、Honda XR、BMW GS、など。小排気量化からビッグオフロードまでいろいろあります。
オフロードバイクには、はやりオフロードのヘルメットが一番似合います。ゴーグルスタイルは特にカッコいい。
ゴーグルスタイルのヘルメットに長らく憧れがあって、いざオフロードのヘルメットを知ってしまうとその軽量と清涼さで今では普段使いになっています。
ただ高速走行に不向きなので、高速道路の利用が想定されるビッグオフロードバイクには、SHOEIのHORNET ADV(ホーネット エーディーブイ)やAraiのTOUR-CROSS 3(ツアークロススリー)などのようにオフロードヘルメットの形をしながらもフルフェイスのようにスクリーンでピタッとフロント部を塞げるモデルもおすすめです。
DUCATIやMVアグスタはイタリアのバイクなので、AGVのヘルメットであればイタリアの風がより色濃く反映され現地のテイストを楽しむことができます。
Harley-Davidsonであれば、アメリカなのでBELLやSIMPSONのヘルメットを合わせてみるなど。国カテゴリーにまとめてみるのもまたコーディネートとして成立します。
もっともダサいのは、自分の身も守らずさらに他人にまで危険を晒すことだと考えています。自分自身にも、他人にもリスペクトの気持ちがなければ何をしてもかっこいいとは言い難い。自分にも他人にも思いやりをもって、心からバイクライフを楽しむことができたら最高です。
自分がカッコいいと思うものを、自ら手にできることを願っています。
バイクの次に必ずゲットしなければならないアイテム、『ヘルメット』。頭は一つですが、ヘルメットは実に豊富なラインナップで数多く存在します。
選ぶ楽しみがある一方で、選びきれずに困ることもあります。そこで、最後のまとめとして今回シェアしたヘルメット選びについて5つのポイントにまとめました。
あなたの最初のヘルメットがどうかベストチョイスになることを心から願っています。ヘルメットは安くはありません。「こんな失敗をした人もいるのか」と、一つの参考としてあなたらしいヘルメットを手に入れてくれたら何より嬉しく思います。
